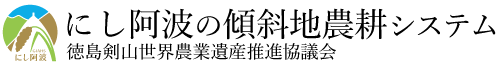農業遺産 傾斜地のあたご柿
半田干し柿部会(つるぎ町)

つるぎ町半田の山間部ではあたご柿の栽培が盛んです。
このうち平良石地区では農家の人たちが集まってあたご柿の干し柿を生産、道の駅で販売し人気を呼んでいます。

ゆうゆう館で販売されている干し柿

あたご柿
半田では、もともと養蚕の栽培が盛んでしたが徐々に養蚕が衰退するにつれて代わりにあたご柿の栽培が増えていきました。
今では50軒から60軒の農家であたご柿を栽培していて四国有数の産地になっています。

平良石地区から見た半田の町並み

柿の木の下にカヤを敷く三好さん
平良石地区では4軒の農家が集まり、つるぎ町干し柿部会として、収穫の終わった12月から2月末にかけて干し柿の加工を行っています。
みんなで持ち寄ったあたご柿をスライスして、網の上にのせて乾燥室で乾かします。
そして温度管理をしながら、まんべんなく乾燥させるために毎朝柿を裏返し、1週間ほどで乾燥して袋詰めにします。

柿の乾燥作業

乾燥室
つるぎ町干し柿部会のメンバーの人達は、それぞれ渋抜きした生のあたご柿を出荷していますが、こうして皆で集まって干し柿の製造をすることを人々の交流の場として楽しんでいます。
代表の三好和人さんは、「作業をしながら農業の情報交換や世間話をする時間が地域の絆を深めている」と話しています。


(干し柿の袋詰め)
この地域でも高齢化が進んでいて柿の収穫や木の剪定などの重労働が難しくなっていますが、干し柿部会の人達はできる限りあたご柿や干し柿の生産を続けていきたいとしています。